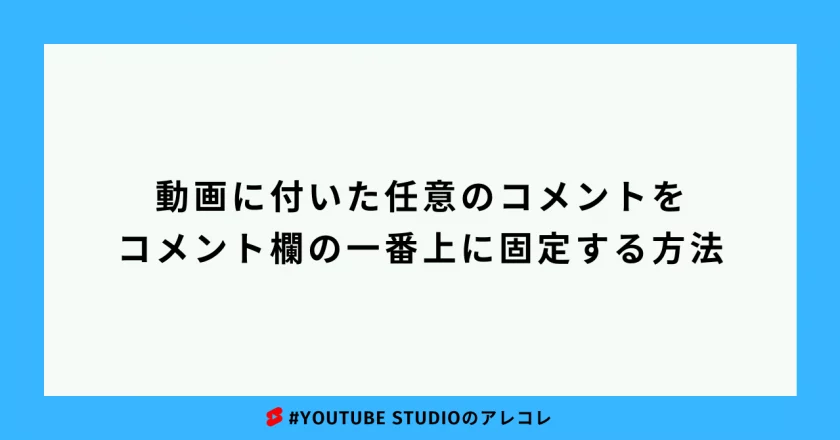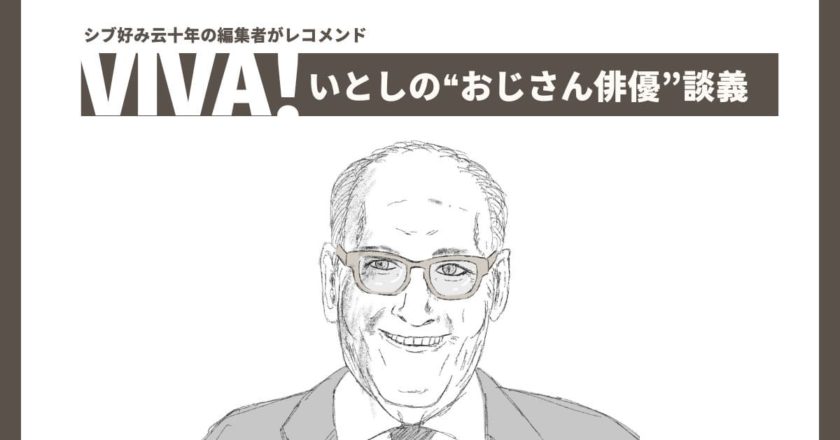Blogブログ
『リバー・オブ・グラス』(94) “何者”でもなく、 “何者”にもなれない人生からの逸脱

“何者”でもなく、 “何者”にもなれない人生からの逸脱
米インディペンデント界の最高峰と言われて久しい監督ケリー・ライカート。じわじわと気になっていた彼女の軌跡を辿ってみようと、94年のデビュー作を観た。
主人公は、マイアミにほど近いアメリカ郊外に暮らす3人の子どもを持つ主婦コージー。オープニングからモノローグで語られる彼女の半生が、しつこいほどに空虚感を運んでくる。母親の家出、家族のためミュージシャンになる夢を諦めて刑事になった父親、通っていた教会では4つの罪をでっち上げて懺悔を繰り返していたこと、学生時代の恋人との結婚に愛はなく、絆を感じられない3人の子どもを、誰かが引き取ってくれる妄想をしていること…。
写真や映像のコラージュで、淡々とつづられるもの悲しい人生の断片。その延長線上で、鬱屈した日々を送る彼女は、折りにふれて、側転をしたりブリッジをしたり、身体をゆらゆらと動かしてダンスをする。ここではないどこかへ。まるでやり場のない想いを発散するかのように、ムチムチした体を使って、気持ちを外へ外へと解き放そうとする。
そんな彼女が、ある晩出かけたバーで、自分と同じように孤独を抱えた青年リーと出会う。意気投合し、酔って忍び込んだ誰かの家のプール。そこでリーの友人が偶然に拾ったという銃をいじっていたコージーは、突然現れた家主に驚いて引き金をひいてしまう…。そこから、2人の逃避行がはじまっていく。
例えば、『トゥルーロマンス』や『テルマ&ルイーズ』、『ナチュラル・ボーン・キラーズ』など、逃避行ムービーにはつきものの、ワイルドさや興奮といった刺激味は、この映画では感じられない。ひとまず辿り着いた安モーテルでは、2人はまるで事件の傍観者のように落ち着いていて、かと思えば、ゴキブリが出た!とパニクっては、聖書や銃で殺そうとするなど、おかしみがそこかしこに、にじんでいる。
共犯関係となったコージーとリーが、安易に“愛”という絆で結ばれないところもいい。孤独な2人にまず必要だったのは、それまで“何者”でもなく、この先も“何者”にもなれない人生からの逸脱だった。
製作時、撮影許可費が払えなかった本作は、ほぼゲリラ撮影で作られたそうだ。ドキュメント感のある生々しさと、16㎜フィルムによるざらついた映像が、コージーとリーの粗削りな感情を伝えてくれる。そしてもう1人…コージーの父親で、夢をあきらめざるをえなかった中年男・ライダーが、人生の悲喜劇を絶妙に体現する。夜間に働き、昼は静かに酒を飲んで日々をやり過ごす彼は、娘が犯行に使った銃の本当の持ち主であり、酔って失くしていた張本人。事件のことも娘のことも全く理解できない彼は、ドラムを叩いては音楽の世界に逃避する。
ライダーがつねに苦虫を噛みつぶしたような顔をしているのにも惹きつけられるが、特に目を見張ったのは、小さな洗面台で、彼が毛むくじゃらの腕を使ってハムスター(ネズミ?)の体を丁寧に洗っているところ。その奇妙な光景の理由はなんとなく明かされるものの、あんな奇妙なシーンは今までに観たことがない。
やがて、ユニークな逃避行が意外な展開を迎えたとき…。コージーは、どこまでも残酷な現実に歯向かうように自らの意志を“暴発”させる。ここではないどこかへ。“何者”かになれる人生へ。それがどんな道行きを示唆するとしても、彼女の新たな人生の門出を祝わずにいられなくなった。