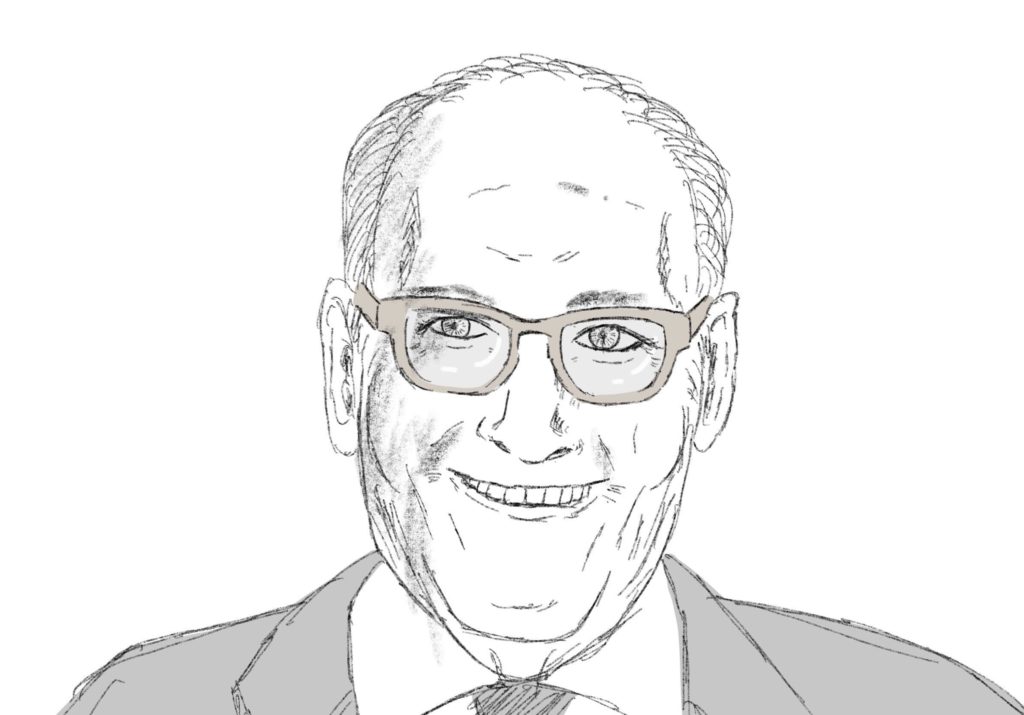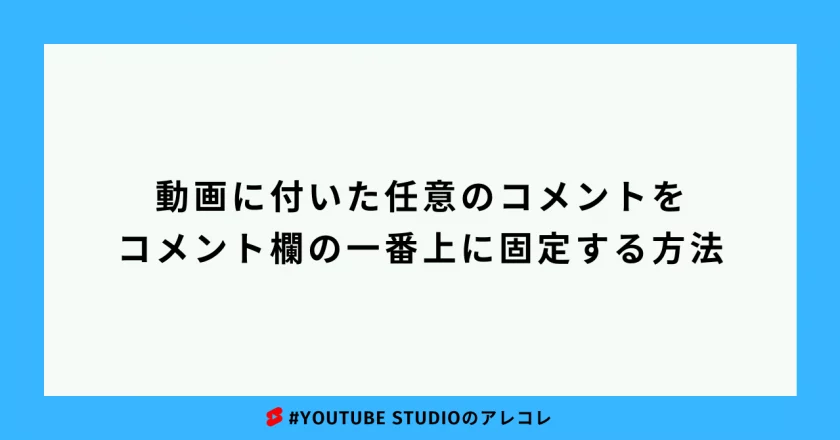Blogブログ
いとしさと、せつなさと、やりきれなさと… 名優リチャード・ジェンキンスの滋味にやられる
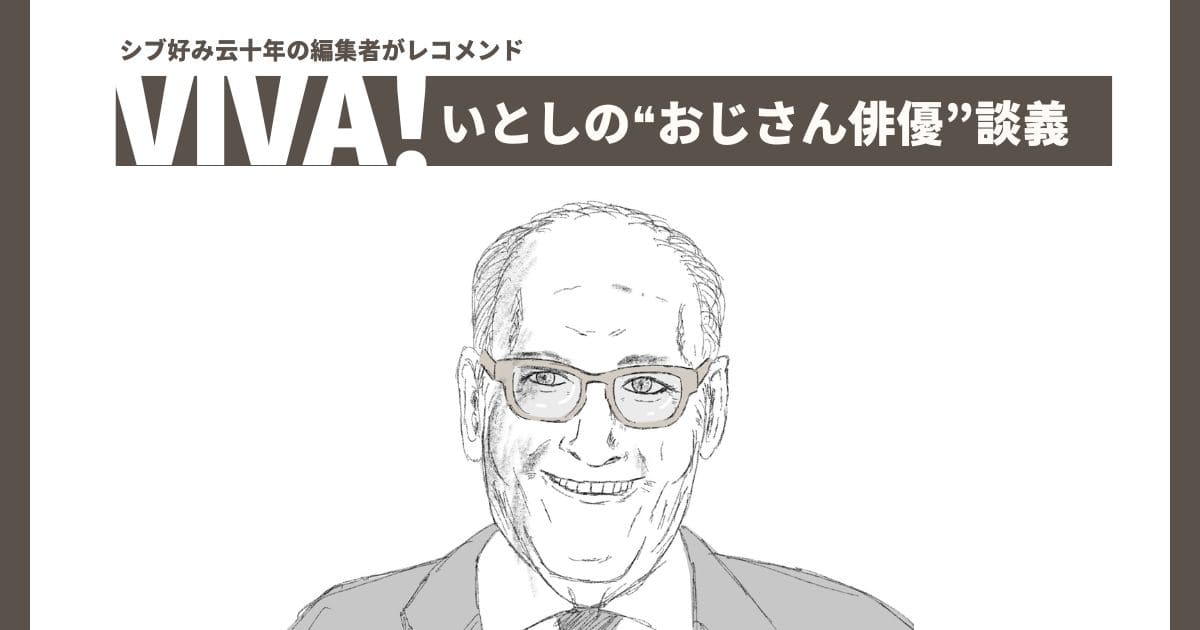
かけがえのない俳優になった『扉をたたく人』
この人を観るだけで、妙にせつなくなってくる。そんな、私にとってのおじさま俳優がリチャード・ジェンキンスだ。
薄い毛髪に短い眉、困ったような表情。年を重ねた貫禄、というよりは、人生の苦みを積み重ねた感のある、哀愁たっぷりのお顔。もちろん役柄に準じてのことではあるけれど、彼の姿からにじみ出るのは、うまくいかないことへの葛藤や、どうにもならないことへの憤り…そうした“やりきれない”想いに、共感させられるのだ。
圧倒的な存在感で主役をはるスターというよりは、物語を支えるバイプレイヤー。近年はギレルモ・デル・トロ監督の『シェイプ・オブ・ウォーター』(17)でヒロインのよき隣人でゲイのおじさま役、『ナイトメア・アリー』(21)での悪辣な大富豪役も印象深い。長いキャリアだけにたくさんの作品に出演しているが、その名優ぶりを決定づけたのはアカデミー賞主演男優賞候補となった、トム・マッカーシー監督の『扉をたたく人』(07)だろう。この作品で私にとっても“かけがえのない”俳優になった。
ジェンキンスが演じるのは、妻を失い無気力な日々を送る大学教授のウォルター。久々に訪れたNYで、シリアからの移民青年タレクと出会い、彼からジャンベ(打楽器)の演奏を習ううちに、友情をはぐくんでいく。
手指を操るように力強く盤をたたき、リズムを生み出していくジャンベ。スーツ姿に不愛想な表情を浮かべていたウォルターが、タレクとの交流やジャンベの演奏を通して、自身のリズムを刻んでいく。はにかむような笑顔や言葉の弾み方に、彼の心が動いているさまがわかるし、何よりジャンベを楽しそうにたたく姿がとても魅力的だ。
やがて不法滞在を理由にタレクが収監されてしまい、ウォルターは彼を救おうと奔走する。自ら弁護士を雇って国を相手取り、仕事もそっちのけに、彼の恋人や母親のモーナに寄り添おうとするのだ。他人の青年のために、彼はなぜそこまでするのか…?その答えは、モーナから「忙しいのに無理することない」と言われたウォルターが「何もかも、なんの意味もない。忙しいふり、働くふりだけだ…」と告げるシーンにある。彼が抱えていた孤独の深さ、閉ざしていた心の扉を開かせた若き友人との時間がいかに大事なものだったのか。結局、ウォルターの力はかなわずタレクは強制送還させられてしまうが、その無情な事実を前にして「我々は無力だ!」とやり場のない怒りを吐きだす彼の姿に、心を打たれない人はいないはずだ。
また、共にタレクを支えるなかで心を通わせていくモーナとの、大人の恋愛模様もいい。窮地のなかで節度を保ちながらも、親密さをどんどん増していく2人の交わす熱っぽい目線や力強いハグは、ときに官能的ですらある。別れ際、モーナはウォルターのことを「いとしい人」を意味する“ハピティ”だと呼んだ。友人もいとしい人も失ったNYで、ひとり残された彼がジャンベをたたき続ける姿を、忘れられない。

人生のほろ苦さを体現した『ラスト・シフト』
『ラスト・シフト』(20)では、ファーストフード店を舞台に、ジェンキンス扮する38年の長い勤務を終えようとしている男・スタンリーが、後任の青年ジェポンに引継ぎをする。この作品でのジェンキンスは、ぽっこりしたお腹もあらわになるTシャツと、デニムのスタイル。大きな体には不釣り合いな小さなリュックを背負って、足をひきずりながら歩く姿に、威厳はない。
酔っ払いへの対応に顔なじみとの慣れたやりとり、掃除の仕方、退屈や眠気との闘いかた。
知られざる深夜勤務のいろはをスタンリーがジェポンに教えていくなかで、会話をかわしたり、ゲームをしたり。その一方、彼から「誰でもできる仕事だ」と言われて傷ついたりもする。
誇りをもって長い間、真面目に働いてきたスタンリーだが、裏方として陽の目を見なかった存在に向けられる社会の目はシビアだ。長いキャリアに最終日、ボスからの特別な祝いを期待する彼に与えられたのは、ほんのわずかな報酬だけ。さらに事故で車がだめになったり強盗にあったりと不運に見舞われたスタンリーは、追い詰められ、ついには、ジェポンを裏切るような行動に出てしまう。許されることではないけれど、彼にはその局面で、やり場のない想いをぶつけるものが、必要だったのだ。
のちに、バスで偶然にジェポンと乗り合わせた彼が、逃げるようにバスを降りてしまうシーンには、思い出すだけで涙が出てくる。情けなさと後悔と恥ずかしさ…その真に迫ったジェンキンスの表情に、人生のほろ苦さが詰まっていた。
『生きる』がアメリカでリメイクされるとしたら、ジェンキンスしかいない
そんな彼の“やりきれない”持ち味が複雑なキャラクターを織りなすのが『ナイトメア・アリー』と、ミランダ・ジュライ監督の『さよなら、私のロンリー』(20)だ。前者は女をいたぶる悪癖のある大富豪、後者は妻と共に娘に犯罪の“英才教育”を施すケチな詐欺師役で、どちらもその行動にまったく共感はできないものの、それぞれに“やりきれなさ”が誤った方向に突き進んだキャラクターになっているともいえる。
『ナイトメア・アリー』の役柄は、あまりハマっていなかったが(彼が女をいたぶるなんて…!)、『さよなら、私のロンリー』のほうは、キモイけれど、とぼけた味わいがあって愛らしく思えるところもあった。もっともこの作品では、ジェンキンスだけではなく、妻役を演じた『愛と青春の旅だち』(82)のデブラ・ウィンガ―や、マリリン・マンソンとの交際も話題になったエヴァン・レイチェル・ウッドという麗しの女優たちが、見た目からしてボサボサ、ボロボロという詐欺師一家役。アーティストでもあるジュライの、ポップかつシュールなテイストに負けない存在感で、芸達者ぶりを発揮していた。
もともと、彼はユーモアのセンスも絶妙なのだ。コメディ作品への出演も多いが、ここではインディペンデント・スピリット賞にノミネートされた『アメリカの災難』(96)までさかのぼりたい。
監督は、のちに『世界にひとつのプレイブック』(12)などでアカデミー賞常連となるデヴィッド・O・ラッセル。ベン・スティラー&パトリシア・アークエット扮する夫婦が、夫の実の親を探すために旅に出るドタバタのコメディで、ジェンキンスはひょんなことから彼らと旅を共にするFBIの堅物捜査官ポール役だ。実はゲイという設定で、公私ともにパートナーであるトニーを演じるのは、いまやアベンジャーズの強敵サノス俳優としてなじみ深くなったジョシュ・ブローリン。若かった当時はギラギラぶりも絶好調で、なかなかの男前。ただジェンキンスのほうはすでに頭頂部が寂しいせいか、現在とあまり印象が変わらない…。劇中ではポールが浮気性のトニーのことをぼやいたり、誤ってドラッグ入りの料理を食べたせいで訳もわからずにパンツ一丁で走り回ったり。四半世紀前からやりきれないキャラを貫いていたのだ。
ただ、どんなにみじめで滑稽でもダメ男に見えないのは、彼自身に品があるからだろう。どこか清潔感のあるたたずまいが、嫌悪感を抱かせないのだ。そこには紳士的な雰囲気さえ感じられる。
黒澤明監督の『生きる』(52)をイギリスでリメイクして話題の『生きる LIVING』(22)では主人公の英国紳士をビル・ナイが演じているが、もしアメリカでリメイクされるとしたら、断然、彼に演じてほしい。ブランコをこぐあの名シーンが似合うアメリカのおじさま俳優は、やっぱりリチャード・ジェンキンスしかいないと思うのだ。